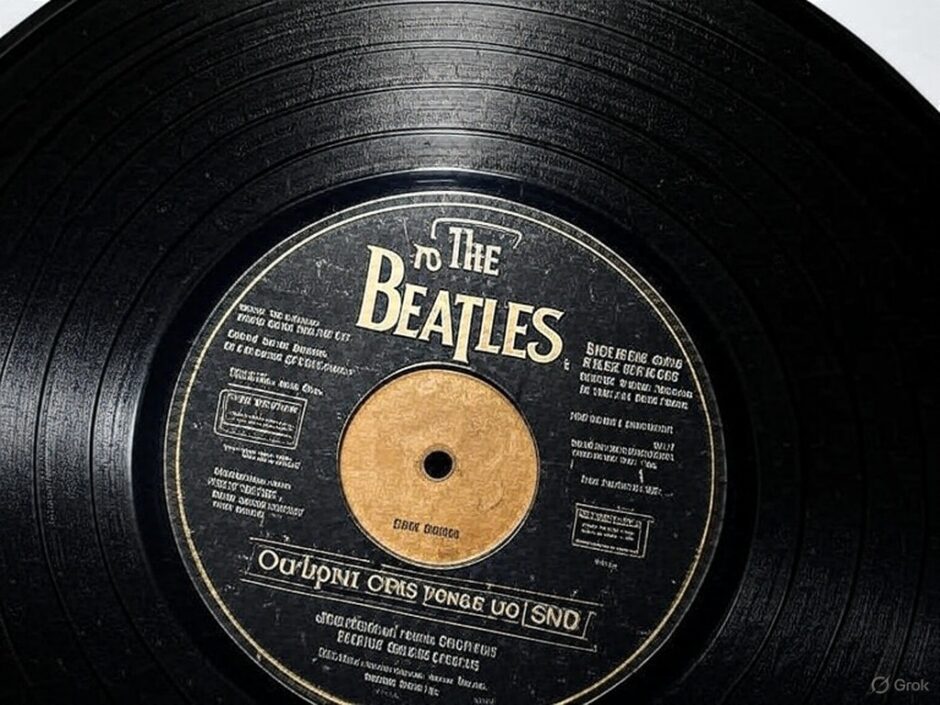- ザ・ビートルズの「新曲」とされる「ナウ・アンド・ゼン」は、AI技術で故ジョン・レノン氏の声を抽出し制作されたことで話題となった。
- このAI活用に対し、一部のユーザーからは「拒否感」や「懸念」といった複雑な感情が示されている。
- 文筆家の門賀美央子氏やブロードキャスターのピーター・バラカン氏は、AIによるボーカル再現や安易な技術利用への忌避感を表明している。
- 音楽作品におけるAIの受け止め方には世代間での違いがある可能性も指摘されている。
AIが実現したビートルズ「ナウ・アンド・ゼン」
dot.asahi.comによれば、1970年に解散したザ・ビートルズの「新曲」として2023年11月に発表され、大きな話題を呼んだ「ナウ・アンド・ゼン」。この楽曲の制作過程では、故ジョン・レノン氏の残したデモテープ音源から、AI(人工知能)技術を使って歌声だけを抽出するという手法が用いられた。かつて1990年代に発表されたAIを用いた楽曲「フリー・アズ・ア・バード」(1995年)や「リアル・ラヴ」(96年)についても、同様の技術で声をさらに鮮明にして再制作する構想があると一部メディアは伝えているという。テクノロジーの進歩により、もはや存在しないはずのビートルズの「新たな姿」を音楽として享受できる時代が到来した。しかし、この技術の進歩と音楽制作のあり方に対し、様々な声が上がっている。
AIによる声の再現への「拒否感」と「懸念」
ビートルズのAIを活用した「新曲」に対し、ユーザーからは複雑な感情が示されている。文筆家の門賀美央子(かどがみおこ)氏(53)は、「ナウ・アンド・ゼン」発表以前の段階で、AIがジョン・レノン氏の声を学習して新曲が作られる可能性を想像し、「絶対に受け入れられないと思った」とXに投稿している。実際に発表された楽曲でのAIの使われ方は予想とは異なり、音質の悪いデモテープからの歌声抽出であったことに安堵したものの、デモテープはジョン・レノン氏にとって未完成なものであり、本人の承認なく世に出して良いのかという違和感は残ったという。
これ、本当に複雑。 ビートルズの”新曲”は聴きたいけど、AIのジョンにはすごい違和感というか、拒否感があるのよ。 今後も故人のデータをテクノロジーで再構成っていうのは出てくるだろうし、いつか普通になるだろうけど、私は受け入れられないし、それで時代遅れと呼ばれるなら甘んじて受け入れる。 https://t.co/sZXsVYoR1W
— 門賀美央子 (@mongamioko) October 27, 2023
BUCK-TICK櫻井敦司氏のAIボーカル案を提案するファンへもショック
門賀氏は、自身がビートルズと同じくらい敬愛する日本のロックバンド、BUCK-TICK(バクチク)の例を挙げる。2022年10月にボーカルの櫻井敦司(さくらいあつし)氏が急死した後、一部のファンの間で櫻井氏のボーカルをAIで再現してライブを行うという案が出たことに、「とんでもない」と強いショックを受けたと語る。門賀氏にとって、歌い手の声はその時の体調や心理状態が反映されたものであり、単なる「音の要素」ではない。AIで合成されたボーカルには「歌っている人間の背景」が一切ないため、ジョン・レノン氏や櫻井敦司氏でそれをやられたら「怒ったと思う」と述べている。
同じく音楽におけるAIの使われ方に懸念を抱いているのは、英国出身のブロードキャスター、ピーター・バラカン(ピーター・バラカン)氏(73)である。「ナウ・アンド・ゼン」については、「嫌いではないけど、とくにすごい曲だとも思わなかった」としつつも、音源からの楽器や声の分離といったAI技術の進歩自体は評価できるとしている。しかし、ジョン・レノン氏の声を生成AIに学習させて全く新たな曲を作るような行為は、「絶対にやっちゃいけない」「亡くなった人の声でそれをやるのは言語道断」と強い言葉で否定的な見解を示している。
「オリジナルな音」からの乖離と世代間の違い
AI技術の進歩は、ビートルズの楽曲のデジタルリマスター技術にも影響を与えている。技術の進化によってより大胆なリマスターが可能になることはファンにとって楽しみである一方、発売当時の「オリジナルな音」から離れていくことへの心配も存在する。ピーター・バラカン氏は、アーティストがそのときに納得して世に出した音が最も信頼できるものであるという考えを示し、自身は必要以上にマニアックなリマスターは求めないタイプだと語る。
音楽のAI利用やリマスターへの受け止め方には、世代による違いがある可能性も指摘されている。ピーター・バラカン氏は、リアルタイムでビートルズを体験した世代は「こういうアルバムの順番で、こういうふうにできあがっていった音楽だ」という概念やオリジナル主義になりがちなのに対し、後追いでファンになった若い世代はビートルズの音楽を「ひとかたまり」として捉えている傾向があるのではないかと推測する。そうした違いがあるならば、音楽の楽しみ方も多様であって良いのかもしれないという考えも示しつつも、自身としては「もうこれ以上はいいのでは」「1970年で存在しなくなった過去のバンド」として、何か新しいことをあえてやる必要はないと考えている。
AI技術が音楽にもたらすものは、新たな創造の可能性とともに、故人の声の尊厳や、アーティストが世に問うた「オリジナル」とは何か、そして音楽体験における技術介入の是非といった根源的な問いを投げかけている。これらの問いに対する受け止め方は、個人の音楽観や世代によって異なり、今後も議論が続いていくことが予想される。
AI技術の進歩と故人へのリスペクトを考える
AIによる音楽制作、特に故人の声を用いた「新曲」という形でザ・ビートルズの楽曲が世に出たことは、多くの人々に驚きと議論をもたらした。門賀氏やバラカン氏の言葉からは、単なる技術的な興味を超えた、アーティストへのリスペクトや「音楽とは何か」といった深い問いが浮かび上がる。特に、AIによって再現された声に「その人自身の背景がない」という指摘は、クリエイティブにおける人間の存在意義を改めて考えさせられる。ファンであってもAI活用への忌避感を抱く層が一定数いるという事実は、技術の進歩が必ずしも歓迎されるとは限らない現実を示している。一方で、技術によって過去の音源から新たな可能性を引き出すことに価値を見出す意見や、世代によって受け止め方が異なるという指摘もあり、AIと音楽の未来は単純な賛否では割り切れない複雑な様相を呈していると感じる。今後、AI技術がさらに進化する中で、アーティスト、ファン、そして社会全体が、音楽におけるAIとの適切な向き合い方を探求していく必要があるだろう。
引用元:dot.asahi.com (AERA)
AIで再現「ビートルズ」の“新曲”に「拒否感」や「懸念」 オリジナルとの違和感は世代による?